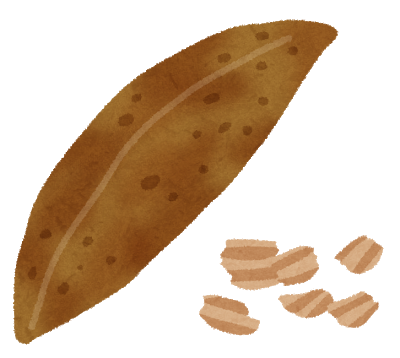平成25年にユネスコ無形文化遺産に登録され注目を浴びている、我が日本の食、「和食」
中でも旨味を味わう「だし」という文化
これは世界に誇れるものです
赤ちゃんの頃からこの文化に触れ、味覚を養っていきたいですね
だし、と聞くとポピュラーなのが昆布だしやかつおだし
2つのうち、かつおだしはいつから使用してよいのでしょうか?回答は、中期食から、です
美味しいだしをとるための正しい方法や、昆布だしについてもお話ししていきます
毎日の離乳食に美味しいだしを使い、しっかりとした味覚を育ててあげましょう
離乳食にかつおだしを使うのはいつから?
離乳食にかつおだしを使用するのは中期食からがよいでしょう
初期食の間は昆布だし、もしくは野菜スープを使用します
昆布だしはかつおだしに比べアレルギー症状を起こしにくいことや、まず食材の本来の味を覚えるという狙いから、初期食の間は昆布だしや野菜スープを使用するのが好ましいと考えます
中期食に移行したら、かつおだしにも慣らしていきましょう
昆布だしとの混合だしにするのもおすすめです
また、大人用のかつおだしでは赤ちゃんにとって濃い場合もあります
大人用には和風だしの素を使用しているという方や、かつお節を使用してだしをとっていても水に対しての目安のかつお節量が赤ちゃん用よりも多いという方もいらっしゃると思いますので、赤ちゃん用にだしをとって製氷皿等を利用して冷凍しておくと便利です
赤ちゃん用のだしについて、水に対しての目安のかつお節量はこのあとご紹介します
昆布とかつおの混合だしにすると旨味アップ!?
中期食に移行し、かつおだしを試すようになったら、昆布との混合だしもおすすめです
昆布にはグルタミン酸、かつおにはイノシン酸という旨味成分が含まれています
それぞれ単独よりも、同時に味わった方がより旨味を感じるのです
このように、お互いの旨味成分が重なると、より一層美味しく感じることを「相乗効果」と呼び、そのおかげで、昆布だし、かつおだし別々よりも混合だしの方が旨味を感じやすくなります
和食ならではの「だしから旨味を味わう」という食経験を、離乳食の時から積ませてあげることで、豊かな味覚の形成に役立つと思います
是非昆布とかつおの混合だし、取り入れてみてくださいね
だしの正しいとり方、教えて!
それでは、かつおだし、昆布だし、混合だしの正しいとり方をご紹介します
1.かつおだし
かつお節 15g
水 1ℓ
<とり方>
①鍋に水を入れて沸騰させ、かつお節を入れる
②弱火にして1~2分煮る
(ぐらぐらと煮たてない方が澄んだだしになる)
③火を止めてかつお節が鍋底に沈むまでおいておく
④ザルを使ってこす
(この時かつお節を絞ってしまうと雑味が出やすいので絞らない方がおすすめ)
2.昆布だし
だし昆布 15g
水 1ℓ
<とり方>
①鍋に水と昆布を入れて30~1時間程おく
②中火にかけ、沸騰直前で昆布を取り出す
(鍋底からフツフツと泡が湧き始め、昆布が動くくらい
入れたまま沸騰させると雑味が出やすいので取り出す
)
③そのまま一度沸騰させる
3.混合だし
かつお節 15g
だし昆布 15g
水 1ℓ
<とり方>
①鍋に水と昆布を入れて30分~1時間程おく
②中火にかけ、沸騰直前で昆布を取り出す
③そのまま沸騰させ、沸騰したらかつお節を入れ弱火にして1~2分煮る
④火を止めてかつお節が鍋底に沈むまでおいておく
⑤ザルを使ってこす
全て水を1ℓと表記していますが、蒸発量やこす作業を加味すると実際のできあがり量は900ml程度になるかと思います
余談になりますが、保育園の給食で、コンソメスープを提供しても子どもたちが「みそ汁」と呼んでいるのが気になり、食育活動の年間計画を立てる際、毎年「だし利き」という回を組み込んでいました
昆布とかつおの混合だし、コンソメ、中華だしの3種類を用意し、子どもたちが香りや少量の味見でグループごとに意見をまとめ、どれがどのだしかを当てるというものです
5歳児を対象に実施していましたが、回を追うごとに「これが一番みそ汁に近い」、「野菜の味がする」等かなり鋭い意見が聞かれ、子どもの味覚の敏感さに驚かされていました
お子さんが大きくなったら、親子で試してみても面白いかもしれません
離乳食にかつおだしを使うのはいつから?【まとめ】
和食とは切っても切り離せない「だし」
正しいとり方で美味しくだしをとって、大人も赤ちゃんも一緒に味わいたいものです
また、だし利きのお話のように、ただ旨味を味わうのではなく、味の違いがわかるようになるのが「豊かな味覚の形成」なのかもしれません
離乳食の頃からだしだけでなく様々な食材の味を経験させてあげたいですね